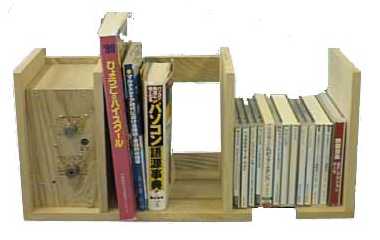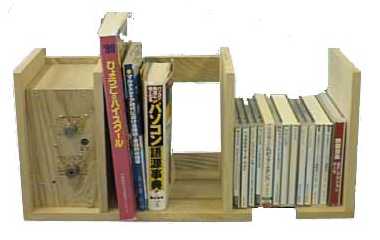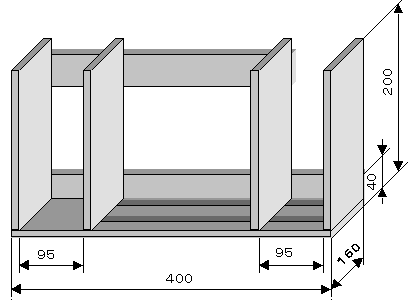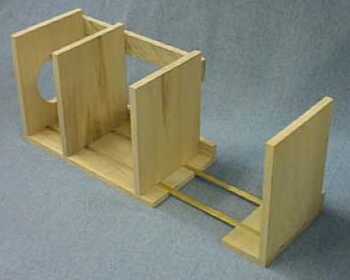マルチ本立て98
三田市技術・家庭科研究会技術部会
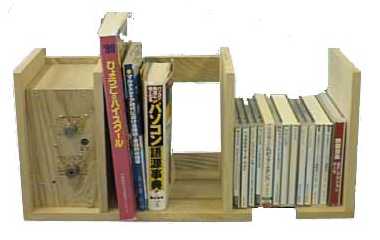
1.主な特徴
(1)本立ての主要材料をセンとし、従来の木材加工の内容を十分に含ませた。
(2)本立て部の一部が拡大し、本やCDなどの収容量がアップするようにした。
(3)拡大用部品に黄銅棒を使用し、金属加工の内容(切断、穴あけ、ねじ切り)を含ませた。
(4)電気学習の、ラジオを組み入れられるように設計した。(左側本立て部)


2.97年度バージョンからの改善点
(1)多くを望みすぎたので、材料と作業のスリム化を図った。
a.全体のサイズを小さくした。← 保管場所に困った。値段が高価になった。
b.箱部と棚を廃止した。← 製作時間がかかりすぎた。値段が高価になった。
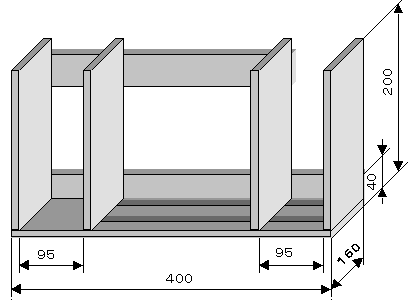
(2)ラジオ組み入れ部を縦にした。
a.音質をよくする → 100mmのスピーカーが組み入れられる。
b.ラジオの枠は、2年で製作することにした。← 転入生の対策
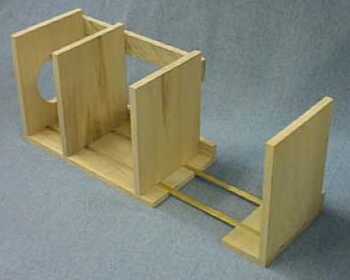
(3)材料の材質を変更した。
a.木部はセンにした。← 接合強度がある。くるいが少ない。
b.くぎをステンレスの丸頭くぎにした。 ← 黄銅の丸頭くぎは曲がりやすく失敗が多かった。
3.必要な工具
(1)木工具
のこぎり、きり(ドリルφ1.5)、菊座きり、げんのう、木工やすり(かんな)
(2)金工具
弓のこ、ハンマ、センタポンチ、ボール盤、機械万力、ドリル(φ4.1)、タップ(M5)、やすり
4.部品一覧表
| 番号 |
品 名 |
規 格 |
数量 |
材質 |
| 1 |
底板 |
12×160×400 |
1 |
セン |
| 2 |
側板 |
12×160×200 |
4 |
セン |
| 3 |
背板(上) |
12×40×312 |
1 |
セン |
| 4 |
背板(下) |
12×40×400 |
1 |
セン |
| 5 |
連結棒 |
4×10×300 |
2 |
黄銅 |
| 6 |
皿ねじ |
M5×12 |
2 |
黄銅 |
| 7 |
仕切棒 |
φ4×300 |
1 |
黄銅 |
|
8 |
釘 |
L=25、丸頭 |
30 |
ステンレス |
| 9 |
接着剤 |
|
少量 |
木工用 |
| 10 |
紙やすり |
#240 |
1 |
|
5.製作指導上の主な注意点
(1)連結棒と底板との接合加工を、まず最初にする
a.機械万力に連結棒を固定し、穴をあける
b.連結棒を底板にはめ込み、底板に穴をあける
c.底板から連結棒をはずし、タップでねじを切る
d.底板の底から、菊座きりでていねいにさらう(あけすぎない)
(2)側板は直角に、かつ平行に立てるようにする
a.側板の加工済み木口を底板側に、生徒の切り口を上にする。
b.ラジオ組み入れ部の側板2枚は、自作ジグ等を用いることで、側板内側寸法95mmの間隔で平行に組立させる。
(3)本体と分離部の分断は、組立後に切断する。
6.本教材の開発から納入まで
(1)設計から試作まで
a.基本設計を本研究部で行った。
b.試作を、開発に協力的な教材会社に依頼した。
c.試作をもとに、本研究部と教材会社でさらに検討を重ねた。
(2)材料の確保および材料の提供方法
a.材料の各校への納入は、納入実績が相当あり、かつ本研究部の研究に協力的だった教材納入業者2社からの納入に決定した。
b.材料の確保および加工については、品質管理の点から、共同研究した教材会社に一括依頼し、納入業者への納入を指示した。
(3)教材の採用と発注
a.採用は各校の裁量によるものとしたが、98年度は全校採用となった。
b.材料の加工の期間を確保するため、発注は97年度中に行った